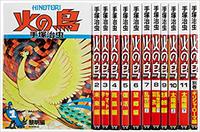2019年05月18日
問屋の贅沢女(世間胸算用より)
井原西鶴の世間胸算用。

社会科(日本史)で、タイトルは習ったでしょう?
江戸時代に書かれた、風刺とユーモアの利いた短編小説集です。
井原西鶴は徹底した現実主義者であり。
現代で例えるとしたら・・・
風刺とユーモアセンスに溢れた、毒舌系の人気お笑いタレント、ってとことでしょうか。
この世間胸算用も。
北野武(ビートたけし)のエッセイ、に近いです(笑)
まあ、この現代語訳を読みますと・・・
江戸時代も現代も、ほんとになにも変わってねえな、と感心します(笑)
現代語訳をご紹介しましょう。
第一巻第一話「問屋の贅沢女」
世の中の定まりごととして、大晦日が闇の夜であることは、天照大神が天の岩戸にお隠れになった神代以来、当たり前のことであるにもかかわらず、
普段の生活に油断して、毎年、大晦日になると、ひとつの計算違いで、年を越す算段ができず、結局、にっちもさっちもいかず困りはてるのは、おのおのの心がけが悪いからだ。
よくよく注意せよ!
大晦日の一日は千両にも代え難い。
銭と銀(かね)がなければ越すに越されぬ冬と春との峠である。
借金の山は高くして、これが峠を越えるのを妨げる大きな手かせ足かせである。
そもそも借金の元は、子供にかかった出費もその一つである。
その時どきには目立たないけれども、一年中に積もりに積もった、たとえば、
廃物となって掃溜めへと捨てられていく破魔弓、手毬(てまり)の糸などの出費を考えてみるがいい。
この他に、
雛祭りのおもちゃの台所道具の擂鉢が割れたのやら、
五月の菖蒲刀の金銀の箔が変わったやつ、
踊りに使う太鼓の破れたやつがあり、
さらに八朔の田実(たのむ)の祝いの雀は数珠玉に繋がれたまま捨てられ、
中の亥(いのこ)の日に祝う餅米、
六月晦日のお祓い団子、
十二月朔日の末子を祝う餅、
節分の厄払いの包み銭、
夢を食う獏の御札を買うなど、
数え上げれば、宝船や車に積んでも余るほどの物入りである。
ことに近年は、いずれにも、問屋の女房どもが贅沢になって、着るものはたくさんあるのに、わざわざそのときの流行の正月の晴れ着をつくる。
それも、羽二重一反四十五匁の白地の絹に一両をかけて、千種(ちぐさ)の細染百色(ほそぞめももいろ)がはりに染める。
高い費用をかけて染めても、人目を惹くこともないのに、あたら金をどぶに捨てるようなものだ。
また、一幅に一丈二尺、一筋につき銀八十六匁もする古渡りの本繻子の帯を腰に纏い、さらに頭には小判二両のさし櫛。
今の米の値段にして、本俵三石分を頭に頂いているようなものである。
腰巻も紅染二枚を重ね、上等の絹の白ぬめの足袋をはく。
昔ならば、大名の内室でも考えられないことである。
思えば、町人の女房の分際として、神仏を恐れぬ所業である。
せめて、自分の余りある金で使えばまだしもだが、雨が降っても晴れても、昼夜の分かちなく、利子を生む借金をした身の上で、このような散財をするとは、贅沢な女どもはよくよく考えて、自分は恥ずかしいと思わねばならない。
明日、分散(自己破産のこと)しても、女の諸道具は差し押さえられないので、分散したあと、それを元手に新たな商売をするのだと思うと世も末である。
そんな状況を、亭主の死んだ親父が仏壇の隅から見て、
冥途からは、浮世の雲を隔てているので、意見を言うのができないのが悔しい。
お前たちの今の商売のやり方は偽りの問屋のやり方じゃ。
銀十貫目の値の物を買い、八貫目で売って金を廻すだけではないか。
結局は財力が衰えるだけじゃ。
来年の暮れには、この家の戸に、『売家!間口十八間、内蔵三か所、居抜き、畳上等品二百四十畳、他に江戸への貨物船一艘、五人乗りの屋形船、これらに小舟を付けて売りたし!来たる正月十九日、町の役所で入札』という貼紙をされ、世間の噂となって、
皆、人手に渡ること請け合いじゃ。
仏のわしにはよくわかるので、とてつもなく悲しい。
この親不孝者!
きっと仏道具も人手に渡るのであろうな。
中にも、青銅でできた花瓶・ろうそく立・香炉の三つ具足は先祖代々のものだから来たる七月の盂蘭盆会の送り火のとき、蓮の葉に包んで、極楽へ取って帰ることにするからな。
どうせ、この家ももって来年いっぱいじゃろう。
お前の心根がそんなことだから、丹波に大きな田地を買って分散したあとの逃げ場所にしようとしても、まことに無意味なことじゃよ。
お前も悪賢いが、お前に金を貸すほどの者はもっと利口じゃ。
お前の財産を一つひとつ調べて、すべての財産が人のものになるのじゃ。
つまらない悪事をたくらむより、何とかもう一度踏ん張って商売を盛り返せ!
わしは死んだが、それでも
阿呆な子でもかわいいもので、こうして、お前の夢枕に立って説教をするぞよ。
よくよく忘れるな!
と言うと、息子は夢の中で、生前の親父の姿をありありと見たが、その夢はさめて、明ければ十二月二十九日の朝である。
寝床の中で大笑いして、
さてもさても、正月まで今日と明日しかないこの忙しい時に、欲深い親父の夢をよく見たものだな。
あの三つ具足は寺にあげちまえ!あの世に行ってまでもふざけた親父だ
と、親父を馬鹿にしている間にも、あらゆる方面から集まった借金取りが山をなすようだ。
(以下、略)
・・・爆!!
ね?なんにも変ってないでしょ?(笑)
あー、笑えたし、明日からまたがんばるかな。。
今朝食った、究極の手抜き朝食がこちら↓

これでじゅうぶん!おいしい!!(笑)

社会科(日本史)で、タイトルは習ったでしょう?
江戸時代に書かれた、風刺とユーモアの利いた短編小説集です。
井原西鶴は徹底した現実主義者であり。
現代で例えるとしたら・・・
風刺とユーモアセンスに溢れた、毒舌系の人気お笑いタレント、ってとことでしょうか。
この世間胸算用も。
北野武(ビートたけし)のエッセイ、に近いです(笑)
まあ、この現代語訳を読みますと・・・
江戸時代も現代も、ほんとになにも変わってねえな、と感心します(笑)
現代語訳をご紹介しましょう。
第一巻第一話「問屋の贅沢女」
世の中の定まりごととして、大晦日が闇の夜であることは、天照大神が天の岩戸にお隠れになった神代以来、当たり前のことであるにもかかわらず、
普段の生活に油断して、毎年、大晦日になると、ひとつの計算違いで、年を越す算段ができず、結局、にっちもさっちもいかず困りはてるのは、おのおのの心がけが悪いからだ。
よくよく注意せよ!
大晦日の一日は千両にも代え難い。
銭と銀(かね)がなければ越すに越されぬ冬と春との峠である。
借金の山は高くして、これが峠を越えるのを妨げる大きな手かせ足かせである。
そもそも借金の元は、子供にかかった出費もその一つである。
その時どきには目立たないけれども、一年中に積もりに積もった、たとえば、
廃物となって掃溜めへと捨てられていく破魔弓、手毬(てまり)の糸などの出費を考えてみるがいい。
この他に、
雛祭りのおもちゃの台所道具の擂鉢が割れたのやら、
五月の菖蒲刀の金銀の箔が変わったやつ、
踊りに使う太鼓の破れたやつがあり、
さらに八朔の田実(たのむ)の祝いの雀は数珠玉に繋がれたまま捨てられ、
中の亥(いのこ)の日に祝う餅米、
六月晦日のお祓い団子、
十二月朔日の末子を祝う餅、
節分の厄払いの包み銭、
夢を食う獏の御札を買うなど、
数え上げれば、宝船や車に積んでも余るほどの物入りである。
ことに近年は、いずれにも、問屋の女房どもが贅沢になって、着るものはたくさんあるのに、わざわざそのときの流行の正月の晴れ着をつくる。
それも、羽二重一反四十五匁の白地の絹に一両をかけて、千種(ちぐさ)の細染百色(ほそぞめももいろ)がはりに染める。
高い費用をかけて染めても、人目を惹くこともないのに、あたら金をどぶに捨てるようなものだ。
また、一幅に一丈二尺、一筋につき銀八十六匁もする古渡りの本繻子の帯を腰に纏い、さらに頭には小判二両のさし櫛。
今の米の値段にして、本俵三石分を頭に頂いているようなものである。
腰巻も紅染二枚を重ね、上等の絹の白ぬめの足袋をはく。
昔ならば、大名の内室でも考えられないことである。
思えば、町人の女房の分際として、神仏を恐れぬ所業である。
せめて、自分の余りある金で使えばまだしもだが、雨が降っても晴れても、昼夜の分かちなく、利子を生む借金をした身の上で、このような散財をするとは、贅沢な女どもはよくよく考えて、自分は恥ずかしいと思わねばならない。
明日、分散(自己破産のこと)しても、女の諸道具は差し押さえられないので、分散したあと、それを元手に新たな商売をするのだと思うと世も末である。
そんな状況を、亭主の死んだ親父が仏壇の隅から見て、
冥途からは、浮世の雲を隔てているので、意見を言うのができないのが悔しい。
お前たちの今の商売のやり方は偽りの問屋のやり方じゃ。
銀十貫目の値の物を買い、八貫目で売って金を廻すだけではないか。
結局は財力が衰えるだけじゃ。
来年の暮れには、この家の戸に、『売家!間口十八間、内蔵三か所、居抜き、畳上等品二百四十畳、他に江戸への貨物船一艘、五人乗りの屋形船、これらに小舟を付けて売りたし!来たる正月十九日、町の役所で入札』という貼紙をされ、世間の噂となって、
皆、人手に渡ること請け合いじゃ。
仏のわしにはよくわかるので、とてつもなく悲しい。
この親不孝者!
きっと仏道具も人手に渡るのであろうな。
中にも、青銅でできた花瓶・ろうそく立・香炉の三つ具足は先祖代々のものだから来たる七月の盂蘭盆会の送り火のとき、蓮の葉に包んで、極楽へ取って帰ることにするからな。
どうせ、この家ももって来年いっぱいじゃろう。
お前の心根がそんなことだから、丹波に大きな田地を買って分散したあとの逃げ場所にしようとしても、まことに無意味なことじゃよ。
お前も悪賢いが、お前に金を貸すほどの者はもっと利口じゃ。
お前の財産を一つひとつ調べて、すべての財産が人のものになるのじゃ。
つまらない悪事をたくらむより、何とかもう一度踏ん張って商売を盛り返せ!
わしは死んだが、それでも
阿呆な子でもかわいいもので、こうして、お前の夢枕に立って説教をするぞよ。
よくよく忘れるな!
と言うと、息子は夢の中で、生前の親父の姿をありありと見たが、その夢はさめて、明ければ十二月二十九日の朝である。
寝床の中で大笑いして、
さてもさても、正月まで今日と明日しかないこの忙しい時に、欲深い親父の夢をよく見たものだな。
あの三つ具足は寺にあげちまえ!あの世に行ってまでもふざけた親父だ
と、親父を馬鹿にしている間にも、あらゆる方面から集まった借金取りが山をなすようだ。
(以下、略)
・・・爆!!
ね?なんにも変ってないでしょ?(笑)
あー、笑えたし、明日からまたがんばるかな。。
今朝食った、究極の手抜き朝食がこちら↓

これでじゅうぶん!おいしい!!(笑)
プロの分筆力ってやっぱりすごい
生物進化は会社経営のヒントになるとおもう(笑)
手塚治虫「火の鳥」
素直に考えましょう。
坂口安吾の言葉
会社というところは、天才と秀才と凡人で動いてるんだそうです。笑
生物進化は会社経営のヒントになるとおもう(笑)
手塚治虫「火の鳥」
素直に考えましょう。
坂口安吾の言葉
会社というところは、天才と秀才と凡人で動いてるんだそうです。笑
Posted by おかもと社長 at 18:28
│読書